初夏の夕暮れ。冷蔵庫のビールが切れていることに気がついて、近所のコンビニまでアロハとゴムゾウリで走る。
よく冷えたBUD(バドワイザー)を何本かカゴに放り込むと、レジで会計を済ませて、小走りに来た道を戻っていく。
コンビニの前では、ガタイのいい男がサラダチキンを、立ったままかじっていた。
BUDを開けて、ひと口。
冷蔵庫から取り出したアジをまな板に並べる。それを包丁で3枚におろしていく。

ゼイゴを取るのはだいぶ上手くなった。しかし、どうしても骨に身が余分に残ってしまうし、刃を入れた断面はガタガタだ。
まあ骨は油で揚げて骨せんべいにするので、少しくらい身が残っていた方がうまい。ガタガタになった部分は、なめろうにでも使おう。
「窓から差した夕日のパイナップル色に、アジのヒレが染まっていた」
包丁を入れながらそんな一文が頭に浮かんで、こういう文章を書く俺の好きな作家がいたな、などと思う。
喜多嶋隆『潮風キッチン』

俺がバドワイザーをBUDと呼んで愛飲するのも、運転が下手なクセに車のハンドルを頑なにステアリングと呼ぶのも、「目つきが悪いので借金取りに見える」と周囲に言われながらアロハシャツばかり着るのも、あるひとりの作家の影響である。
作家の名前は、喜多嶋隆。
湘南・葉山エリアを中心に、海沿いを舞台にしたスピード感のある、クールな小説を多数発表してきた小説家だ。
俺がこうして不器用ながら、毎日のように魚屋に通い、魚を捌く練習を始めるキッカケになった『潮風キッチン』シリーズもまた、彼の近作である。
あらすじ
葉山の海辺に住む主人公、海果(うみか)は18歳。
ある日突然母が男と失踪したことで、多額の借金返済のため、祖父の代から続く居酒屋を引き継いで飲食店を始めることになる。
彼女は偶然知り合った、自分と同じような境遇の中学生、愛と共に、漁港で売り物にならず弾かれた魚を仕入れながら、シーフード料理の店を経営していく。
地元の漁師や、撮影に来たタレント、信用金庫の職員などを巻き込み、物語は進む。
文庫本の隙間から森戸や材木座海岸の波の音が聞こえてきそうな、爽やかな一冊だ。
正義の味方になりたいわけじゃないけれど

周囲の大人たちの優しさに触れながらも、海果たちの店の経営は、常にギリギリだ。
だからこそ売り物にならない、弾かれた魚を使わなければならないし、限りある食材は少しも無駄にすることはできない。
俺はこの本を読みながら、一般的な家庭のひとりっ子として、食べることに不自由したことがなく、それなりの贅沢を与えられながら育った我が身を振り返ることになる。
「食べ物を粗末にして生きてきた」という自覚はない。
俺は出されたものはなんでも食べるし、好き嫌いもない。お茶碗にご飯粒を一粒も残すな、という教育も受けてきた。
それでも、俺が居酒屋で口に運んでいる小綺麗に盛り付けられた料理、あるいは仕事帰り何も考えずに買っているコンビニ弁当の裏には、多くの廃棄が存在している、ということに関して随分と無頓着であった。
フードロス、という言葉が叫ばれるようになって久しい。
そして、子供の貧困、もまた然り。
じゅうぶん食べられるのに売り物にならないと弾かれた魚たちを見て、親に見放された海果と愛が、まるで自分たちのようだ、という思いにふけるシーンがそれを象徴している。
爽やかな葉山の海を舞台にしたハートウォーミングな物語でありながら、この問題提起はとても根深い気がする。
だからといって、俺は何もそれらの問題を解決する正義の味方になりたかったわけじゃない。俺には飢えた子供を救うことはできないし、フードロスを根絶する力もない。
だからこれは言うなれば、『食い意地』である。
魚の頭や骨で出汁をとったあら汁は美味しいし、スーパーでパック詰めされたカット済みの刺身を買うよりも、自分で捌いたほうがはるかに割安で、たくさん食べられる。
日々の酒代と痛風の治療費が家計を圧迫している俺にとって、晩酌のサカナ代が浮くのはありがたい。
毎日の仕事終わりの一杯は、ケチって買った発泡酒ではなく、軽やかな香りが全身を駆け巡るようなBUDであってほしい。
タコ飯、マヒマヒバーガー、アジフライ、シーフードパスタ、ヤリイカのトマト煮…。
このシリーズに登場する、葉山の海で採れた新鮮な魚介類を使った、海果の作る料理の数々が、読者の食欲を刺激することは間違いない。
ページをめくるたび、ジュワッと口の中いっぱいに唾液が広がるのを感じる。
読み終わった後は、シーフードを食べたくなること請け合いだ。
骨までしゃぶるお兄さんは好きですか?

先述の通り、酒が好きだ。そして食べることも好きだ。
食べられるものは、骨の髄までしゃぶりたい。いや、なんなら噛み砕きたい。
一部の小さな魚の骨は、油で揚げればカラッとした骨せんべいになる、というのもこのシリーズで学んだことのひとつだ。
自宅で揚げたてアツアツ骨せんべいを、冷えたBUDで流し込みたければ(よく噛もうね)自分で作るしかないだろう。
余った頭や捌き損なった身は、味噌汁にぶち込んでおけば極上の「フードロスゼロ汁」もとい、あら汁の完成である。
二日酔いの朝なんかにこれが鍋にあると、最高に嬉しい。眼球まで舐めちゃうぞ。
と、いうわけで。
こうしてパイナップル色の夏の夕暮れ、必死こいて安物の包丁で魚を捌きまくっているという次第だ。鱗が頬に張り付いて、汗が目に染みる。
腕前の方はまだまだである。海果に弟子入りしたい。
飽食の国、日本。
金さえ払えば食べられないものはない。もちろん、そんな国・時代に生まれたことそれ自体は幸福なことである。
しかしそれ故に、食べること・飲むことに人々があまりにも無関心すぎるような気がする。
美食や飲酒を娯楽として享受することはあっても、その過程には恐ろしく無関心だ。
そして、栄養に関する知識が広まるのに比例して、食を楽しむこと自体に関心のない人々も増えた。
完全なバランスで栄養が取れるという弁当やパンが流行り、サプリメントで不足した栄養を補い、マッチョはサラダチキンをコンビニの前でかじる。
もちろんそれは悪い事ではないし個人の勝手だが、食いしん坊の俺からすると、どうも味気ないような気がしてしまうのだった。
今宵もアロハとサカナとBUD、で乾杯

このサイトを立ち上げた背景には、そんな思いもあったりなかったりする。
ただ日々の酒と飯を、面白おかしく楽しみたい、という純粋な思い。
同時に、それらをより楽しむにはもう一歩、こちらから踏み込んで近づいていく必要があるのではないか、という思い。
少し大袈裟かもしれないが、そんな少し大袈裟なコンセプトと「うまいサカナで酒飲みてえ〜」という即物的な欲求を組み合わせて「フィッシュ(酒)ストーリー」という名前をつけた。
フィッシュストーリー。
意味は、そのまま「大袈裟な話」
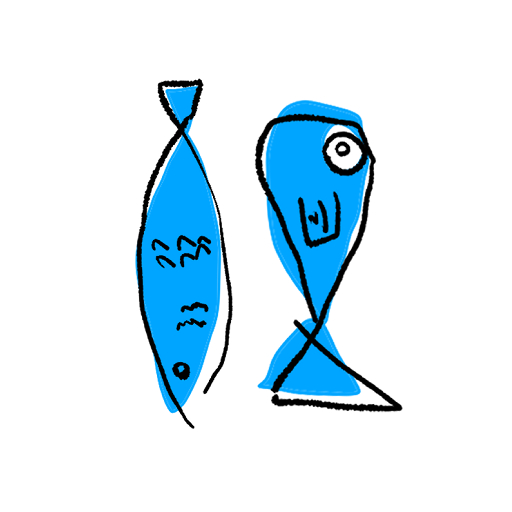
なんのことはない。ただ30代の(ちょっとハンサムな)お兄さんたちが、酒を飲み歩いたり、飯を作ったり、犬と散歩したり、二日酔いの昼下がりに本を読んで感銘を受けたりしている姿を紹介するだけだ。
さて、今夜も晩酌を始めよう。
もちろんビールはよく冷えたBUD。アテは自分で捌いたちょっと不恰好な魚たちだ。











